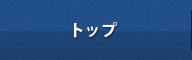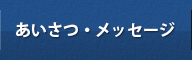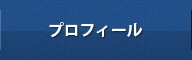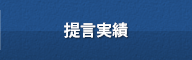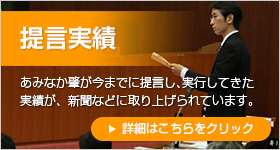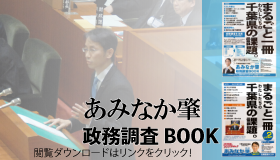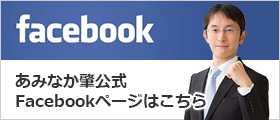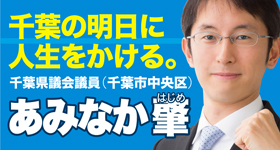2014.02.17 - ブログ
平成25年4月1日現在の千葉県の公立学校(高校)の耐震化率は、79.9%で全国順位は32位となっています。全国平均は86.2%であり、千葉県はこれを下回っていることとなり、早急な耐震化の推進が必要です。

実際の数ベースでは、全棟数778棟中、耐震性を有するもの622棟(昭和57年(新建築基準法施行)以降に建築されたもの254棟+昭和56年以前に建物されたもので耐震性がある・耐震改修されたもの368棟)となり、耐震性のないもの156棟となります。

なお、東京都や長崎県は耐震化率100%を達成しています。
こうした事態を受けて県教育庁は、県立高校の校舎・体育館等で耐震診断の結果、補強を要すると判定された建物について、補強工事を実施し、平成27年度末の完了を目指し、来年度分(平成26年4月~)の県立学校耐震化推進事業として、予算額約84億7千万円を計上しました。

その内訳は、構造設計(43棟分)及び意匠設計(46棟分)の工事設計費として約1億7千万円、耐震改修工事費(51校、56棟分)として約61億9千万円が予算計上されています。
耐震改修の流れとしては、
構造設計 → 意匠設計 → 耐震改修
と進みます。
その他、耐震補強が困難で建替えが必要な東葛飾高校、銚子高校の改築費用として、16億3千万円等が計上されています。
なお、県立特別支援学校の耐震化は平成23年度で完了(耐震化率100%)しています。
あみなか肇は、引き続き着実な県立学校の耐震化の推進について、県教育庁の対応を注視して参ります。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.02.15 - ブログ
先日、当ブログでも取り上げた、千葉県は平成25年中の自動車盗の件数が全国ワースト1である問題。

その原因の一つでもあると考えられる、不法ヤード対策として、県は「(仮称)千葉県ヤード設置適正化条例」素案を発表し、パブリックコメントを実施しています(平成26年2月13日~3月11日)。
ちなみに、全国のヤードの約2割が千葉県に集中(473件:平成25年12月末現在)し、その7割が印旛地域に集中しているとも指摘されています。
素案ではヤードの定義、ヤード事業者が講ずべき措置、報告の徴収、立入検査、勧告、命令、罰則等について規定しています。
罰則部分について、今後、検察協議を実施し、協議が整い次第、上程するとのことです。
当条例は、ヤードの適正な設置に係る全国初の条例となると思われます。
ある行政課題に対して、地域の実情に合致した独自条例を制定し、それを活用して行政課題の解決を図り、政策を実現していくという観点からは、これら一連の県の対応は高く評価されるべきものと考えます。
不法ヤードが多く存在すると考えられている埼玉県、愛知県、茨城県、神奈川県等にとっても参考になる条例であると思われます。
引き続き、当条例の実効性の確保等について県の対応を注視していきます。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.02.13 - ブログ
ファシリティマネジメント(FM)が各自治体で導入されています。
FMとは「企業・団体等が保有又は使用する全施設資産及びそれらの利用環境を経営戦略的視点から総合的かつ統括的に企画、管理、活用する経営活動」とのことです(公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会(JFMA)による。)。

都道府県レベルで最初に導入したのは三重県で、平成12年頃とも言われています。
FMが取り上げられるようになった背景としては、
・自治体をとりまく財政状況が厳しいこと
・その要因でもあるが、人口減少・少子高齢化の進展が著しいこと
・高度経済成長期に集中的に建設された施設等の老朽化・それに伴う更新の時期が到来していること
・施設の更新・維持・管理等が行政の縦割りの中で検討され、部局横断的な、一元的な管理ができていないこと
等が指摘されています。
このような状況の中で、これまで千葉県では組織を設置してのFMへの取組はなされておらず、管財課で数人の職員が担当していましたが、今回の組織改正でようやく総務部内に「資産経営課」が設置されることとなりました。
あみなか肇は度々その必要性を県に訴え続けてきましたが、今回ようやくこれが実現しました。
ちなみに、資産経営課の新設によって、課が増えますが、他課の統合等によって、県庁の全体の課の数に変更はありません。焼け太りのないよう、そこは厳しくチェックしていきます。
県有施設の現状は、庁舎等約2000棟、広さ350万平方メートル。
そのうち、40年以上経過した建物が約2割、20~39年経過している建物が約6割存在しており、早急な対応が必要となっています。
仮に、今後、単純にすべての建物について建て替え・改修等を実施するとすれば、今後10年間に必要となる経費は約3200億円と見込まれています。
今後は資産経営課が設置されたことによって、これら施設の廃止・集約化、長寿命化、全体としての最適化などを図り、財政負担の軽減・平準化が図られることが期待されます。
その一方で施設の廃止等は、地域に大きな影響を及ぼすことから、その手続等について、県の対応を注視して参ります。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.02.10 - ブログ
私と同世代の子育て中の親御様から、「他県の子ども医療費助成は充実しているのに、千葉県は・・・」、「子ども医療費助成が充実すれば、より安心して子育てできる・・・」などといったご意見を頂戴することが多くあります。

子ども医療費助成制度は、乳幼児や小・中学生等の医療費の患者負担分を自治体が助成する制度で、患者世帯の経済的負担を軽減する、又はゼロにするという制度です。つまり自治体による「子どもの医療費無料化」といえる制度です。
現行の公的医療保険制度では、子どもが医療機関の窓口で支払う自己負担率は2割若しくは3割となっていますが、子ども医療費助成制度は、患者の自己負担部分を自治体の公費でカバーするものです。
この制度は、すべての都道府県で実施されている(助成対象年齢等にはかなりの差がある。)ものの、国からの財政的な援助は全くなく、すべて都道府県及び市町村の独自事業として実施されています。このため、自治体によって制度の内容が異なります。
また、制度の実施主体は市町村ですが、その費用は都道府県も負担しています。
なお、千葉県では、子ども医療費助成制度に要する経費について、県が制度化している部分については、県と市町村が2分の1ずつ負担しています(千葉市を除く。政令指定都市である千葉市の子ども医療費助成に係る経費のうち、県が負担するのは4分の1)。
そして、市町村が独自に実施している、県の制度を超える部分については、市町村がすべて負担することとなります。
そこで、まず、千葉県の子ども医療費助成制度をみると、入院については中学校3年生まで、通院については小学校3年生までが助成対象となっています。
これらの助成対象を、全国と比較したものが以下の表です。
都道府県の子ども医療費助成制度の実施状況

平成25年12月現在
千葉県は、入院については、全国トップ(福島県は原発事故の特殊要因があるため、ここでは考慮しない。)となっています。
同様に通院をみると、最も充実している都道府県は中学校3年生、その次が小学校6年生、その次が小学校3年生であり、千葉県は3番手に属していることが分かります。
したがって、千葉県の子ども医療費助成を全国レベルでみると、入院については全国でも最も充実しており、通院についてもそれなりに充実しているものの、まだ拡充の余地がある、といった位置づけであると考えます。
次に、県内の市町村の状況をみたものが、以下の表です。
千葉県内の市町村の子ども医療費助成の実施状況

平成25年12月現在
いすみ市が入院・通院ともに高校3年生まで、一宮町が入院・通院ともに高校1年生までと、これら2市町の助成対象が突出していることがわかります。
また、入院については、上記2市町以外の52市町村は中学3年までに集中している一方、通院については、小学3年、小学6年、中学3年の3つに分散しており、最も多いのが中学3年の32市町村となっています。
これらを見ると、財政的に豊かな自治体が、助成対象の範囲を広げているともいえず、様々な要因、例えば、近隣市の状況等によって大きな影響を受けているものと考えられます。
今後のこの制度の拡充の方向性、及び県と市町村の費用負担のあり方ですが、都道府県レベルで見れば、すべての都道府県で当該助成事業を実施しており、その助成範囲としては小学校就学前が最も多くなっています。
これら県民のニーズを踏まえて全国的に広く実施され定着しているものについては、もはや国民的ニーズがあるといえることから、この部分までは国の事業として実施し、国が費用負担するということも考えられるのではないでしょうか。
そして、千葉県内の市町村の場合、入院、通院ともに、助成対象として最も多いのは中学3年であることから、国が負担すべきと考える小学校就学前を超える部分から中学3年までは、県と市町村で2分の1ずつの費用負担とし、それを上回る部分は市町村の独自事業として市町村が負担するということも考えられます。
そうすることによって、国・県・市町村の役割・財源負担を整理するとともに、千葉県の子ども医療費助成の対象を、自治体の負担を増加させることなく、入院・通院ともに中学3年生までに拡充することができるのではないでしょうか。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.02.06 - ブログ
本日、警察庁から平成25年の犯罪統計の確定値が発表されました。
それによると、千葉県における、平成25年の自動車盗の認知件数は3,295件と、大変残念ながら、全国で断トツのワースト1位となってしまいました。ワースト2位の愛知県の2,712件、ワースト3位の大阪府の2,466件を大きく上回ってしまっています。

また、千葉県の平成24年の自動車盗の件数は2,380件であったため、昨年度比915件と大幅な増加となっています。
こうした事態を受けて、県は、本日概要説明のあった来年度予算において、不法ヤード対策事業、主として捜査支援システムや捜査用ビデオカメラの整備及びヤードへの立入調査などを実施するための予算として、約7300万円を計上しました。
以前にも言及しましたが、千葉県で自動車盗が多い原因としては、ヤード(自動車の解体工場)が多数存在する(県内に約470か所)、都市部に近い、道路網が発達している、港が近いことなどが考えられます。大多数のヤードは健全に事業を行っていますが、ごく一部のヤードにおいて自動車窃盗グループがヤード経営者と結託をして、盗難車の解体作業場に利用している実態があります。
このため、県と県警は、各種法令に違反した行為が行われている不法ヤードを規制し、ヤードの適正な設置を図るため、「(仮称)ヤード設置適正化条例」を制定し対応することとしています。
あみなか肇は去る平成24年2月議会一般質問において、不法ヤードが盗難車両の解体、不正輸出の作業場となっているほか、不法滞在外国人の稼働、蝟集場所や薬物の使用、隠匿場所として利用されるなど、犯罪の温床となっている状況が見られ、治安上の大きな問題になりかねないことから、こうした不法ヤードに対しては、地権者に契約解除を働きかけるなど、総合的なヤード対策・自動車盗対策に取り組むことを強く要望していますが、引き続き、県及び県警のより積極的な対応を要望して参ります。
千葉県議会議員
あみなか肇
« Prev
Next »