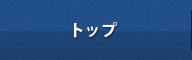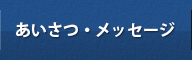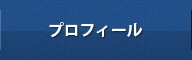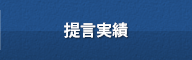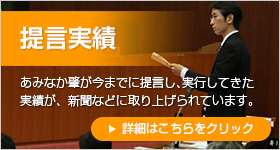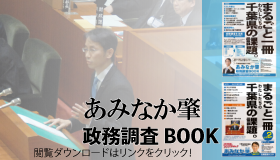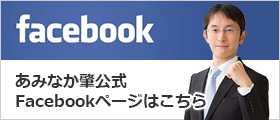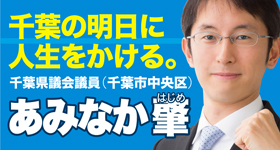2014.07.25 - ブログ
先日、当ブログで取上げた、千葉県内の危険ドラッグ店が9店に増加している問題(http://ameblo.jp/hajime-aminka/entry-11898105952.html
)。

本日の産経新聞で報道されています。
それによると、危険ドラッグの使用が疑われる人身事故が今年になって3件発生しているとのこと。
また、記者が実際に危険ドラッグ販売店に行き、内部を取材した様子も書かれています。
脱法ドラッグの安易な使用に警鐘 人身事故3件、販売9店 千葉(産経新聞)
2014.7.25 04:02
http://sankei.jp.msn.com/region/news/140725/chb14072504020003-n1.htm
脱法ドラッグ(危険ドラッグ)の使用者が絡む交通事故が相次いでいる問題で、県内でも疑いのある人身事故が今年になって3件発生しているほか、ドラッグの販売も千葉、船橋などの9店で確認されていることが24日、県警への取材で分かった。若者らが少ない知識で手を出している実態が問題視されており、捜査関係者らは安易な使用に警鐘を鳴らしている。
◇
人身事故は1月に1件、6月に2件発生し、いずれも自動車運転過失致傷罪や、5月20日に施行された自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)=いずれも7年以下の懲役・禁錮か100万円以下の罰金=で摘発されている。押収したハーブなどに危険な薬物が含まれ、正常な運転ができない状況だったと立証されれば、より重い同法違反(危険運転致傷)=15年以下の懲役=などに切り替えられる予定だ。
車内からは薬物や植物片なども発見されているが、サンプルとの比較など鑑定にはかなり時間がかかるという。県警交通捜査課の幹部は「運転者の使用が疑われる自損事故も数件ある。重大事故を起こす前に芽を摘みたい」と話している。
・死亡例も
4月の薬事法改正により、販売に加えて使用、所持も摘発対象となった。このことにより、交通事故を起こした使用者以外の摘発もみられている。今月22日には、行徳署が指定薬物(通称PV9)を含む植物片を所持していたとして、無職の男(55)を薬事法違反(所持)の疑いで逮捕した。
同署によると先月上旬、路上で寝ていて110番通報された男は、ドラッグの使用後で酩酊(めいてい)状態だった。署員が自宅まで同行すると、目の前で再び吸おうとしたという。男は「使ったことは認めるが、捕まるとは思わなかった」という趣旨の供述をしているといい、成分や効果を把握せず、安易に手を出していたことが浮き彫りになった。
使用後に倒れて119番通報されるなど、県警が使用を把握しているケースは昨年1年間で39件あった。過去には死亡例もあるといい、対策は急務だ。
5月に勝浦市での殺人で同罪などで逮捕、起訴された男(34)も、自宅で覚醒剤や大麻とともに指定薬物を含んだハーブを所持していたとして、薬事法違反でも逮捕された(同違反は不起訴処分)。法改正後間もないため、摘発は手探りの部分もあるが、包囲網は狭まりつつある。
・中身は不明
県警薬物銃器対策課によると、県内で脱法ドラッグを販売しているのは、千葉、船橋両市の各3店と柏市2店、松戸市1店の計9店。これまで県警が販売店側を摘発したのは、「脱法ドラッグ」と称し、幻覚作用のある薬物を販売した千葉市稲毛区の店舗を、麻薬取締法違反(営利目的所持)で平成24年に摘発した1件のみ。このケースでは、店側も中身を把握していなかったとされる。
県警幹部は「鑑定してみないと、何が入っているか分からず本当に危険。一度手を出したら取り返しがつかなくなる」と使用しないよう呼びかけている。
◇
・店員「使うなら家で」 本紙記者が販売店へ
深夜、県内の脱法ドラッグ販売店に記者が足を運んだ。繁華街の裏路地にひっそりとたたずむ店舗。看板はあるが、何を販売しているのかは全く分からない。知っている人以外の訪問者はいないだろう。
中はわずか3畳ほど。「輸入雑貨店」を装う店もあるというが、ここには数センチ四方の小袋に入った怪しいドラッグだけが、小さなショーウインドーに並んでいる。それぞれ価格は数千円と書かれている。
店員の男は30~40代ぐらいだろうか。気さくな様子で話をする。「使っても逮捕されないのか」との問いには「たぶん、大丈夫なんじゃない」。あまり知識はないのか、使う人間に興味はないのか、さらっと言ってのけた。「人によって効果は違うけど、アルコールみたいな感じですよ。お客さん、初めてなら500円分でいいですよ」と話す。
「でもやるなら、必ず家でやってくださいね。車の運転とかされると今、問題になっているし困るから」
危険性は認識しているようだ。多いときでは1日に数十人来るという。無理やり買わせようとする雰囲気はなく、購入を断って外に出た。(山本浩輔)
◇
【用語解説】脱法ドラッグ(危険ドラッグ)
覚醒剤や麻薬などと同様の作用があり、違法と合法の境目にある薬物の総称。ハーブと調合したものや粉末状のものなどがある。薬事法で指定されていない「脱法」の薬物、指定されている同法違反の薬物の両方を含む。ハーブはたばこのように直接点火したり、器具を使ったりして吸引する。
(以上引用)
危険ドラッグをめぐっては、国でも各種の対応がなされていますが、県としても条例を制定するなど積極的な対応が必要と考えます。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.07.24 - ブログ
先日当ブログでお知らせしたPED(豚流行性下痢)、当該記事の中で言及したとおり、この7月をもって本県では一定の収束といえる状況になったとのことです(http://ameblo.jp/hajime-aminka/theme-10082117956.html
)。

具体的には、6月中旬以降、本県でのPEDの発生件数は毎週2件程度で推移する一方、沈静件数は10件前後で推移し、7月16日~同22日にかけての発生件数は0件であったとのこと。
このようにPEDの新たな発生は散発的になっていること、ワクチンの供給が十分であること、発生農場の7割が沈静化していることを受けて、県は、これまで設置していた消毒ポイントでの車両消毒を明日をもって終了し、今後は各農場ごとの衛生対策の指導等に切り替えて防疫対策を実施していくとのことです。
油断はできませんが、県の迅速な対応によりPEDが沈静化したと判断できる状況になったことは評価されるべきと考えます。
引き続きの県の適切な対応を要望して参ります。
PED被害10億円超(読売新聞)
2014年07月24日
県は23日、豚の伝染病「豚流行性下痢(PED)」による県内での被害額が10億円を超えることを明らかにした。発生は収束に向かっていることから、県による感染拡大防止のための消毒ポイントは25日に解除する一方、来月から毎月1日を「一斉消毒の日」と定めて対応を強化する。
県畜産課によると、県内では18日現在、14万5263頭の感染が確認され、そのうち4万243頭が死んだ。県が死んだ豚に加え、親豚の発育不良、流産などによる被害をまとめたところ、総額は概算で10億円を超えることが判明した。
県内111か所で確認された感染は、約7割の83か所で沈静化している。完全な封じ込めはできないとされるため、県は25日で、旭市や香取市など5か所で行ってきた消毒を中止し元の体制に戻すことにした。
ただ、県は今回の感染の教訓から、再発防止に向けては畜産農家による消毒作業の徹底が重要と判断。業界団体などと連携し、8月1日から毎月、〈1〉車両の消毒確認〈2〉立ち入り者の衣服交換〈3〉消石灰の散布――など、7項目のチェックの徹底を畜産農家に求める。
同課は「日頃行っている消毒を月に1度点検することで、伝染病の侵入リスクの低減と意識の向上を図りたい」としている。
豚流行性下痢が沈静化 車両の一斉消毒終了へ(朝日新聞)
2014年7月24日03時00分
県は23日、この春から県内の養豚農家に大きな被害をもたらしてきた豚流行性下痢(PED)の発生数が減ってきたため、旭市など県内5カ所で実施してきた車両の一斉消毒を25日で終えると発表した。今後は農家の啓発に取り組むことで、発生の防止に努める。
PEDは人には感染しないが、生後まもない子豚がかかると高い確率で死亡する。県によると3月27日以降、県内の養豚農場の3割近くにあたる111農場でPEDが発生して約14万5千頭が発症、4万頭あまりが死亡した。死亡や発育不良による被害額は10億円を超えるとみられる。
7月に入ってからも、県北東部や中部で6件の発生が確認されている。だが、ピーク時に比べると散発的でワクチンの供給も進んだことから、25日で消毒地点を設ける形での車両の消毒を終えることにした。一部の市は独自に消毒地点を設けてきたが、これも月内ですべて終了するという。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.07.22 - ブログ
本日、厚生労働省と警察庁は脱法ドラッグの新名称を「危険ドラッグ」としたと発表しました。
また、ここのところハーブとして販売されている危険ドラッグの使用が原因とみられる自動車の暴走運転等による事故が相次いで報道されています。あるケースでは容疑者が「よだれ」を垂らしている事故直後の様子も報道されました。

千葉県内における危険ドラッグ店の状況は下のとおりです。大変残念な結果ですが、10か月間で3店舗増加してしまっています。

報道によれば、大阪府では、府内に約40店舗ある危険ドラッグ店すべてに立ち入り調査を実施するとのこと。
本県においてもしっかりとした厳しい対応が求められています。
また、店舗だけでなくインターネットでの販売に対する対応も求められています。そのためには国、各都道府県及び警察が連携して取組む必要があります。
なお、千葉県では、本年度予算において、乱用による健康被害や犯罪への悪用等が問題となっている危険ドラッグの取り締まりを進めるべく薬物の分析検査体制を強化するためなどの予算として約7,700万円を「違法ドラッグ対策事業」として計上しています。これを有効に活用すべきと考えます。
また、以前にもご案内しましたが、千葉県議会としても、平成24年6月議会において国に対し、違法ドラッグとりわけ脱法ハーブ等に対する指導取り締まり等の強化について、速やかに適切な対応を行うよう、意見書において強く要望したところです。
この意見書の作成にあたっては、あみなか肇が案を作成し、各会派の賛成の下に可決されました。
あみなか肇は、引き続き、危険ドラッグに対する国及び県の適切な対応を求めて参ります。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.07.17 - ブログ
先日の新聞報道で、都道府県における人口減少に係る対策組織の設置状況について報道されていました。

千葉県では、5月23日に「千葉県人口減少・少子化対策推進チーム」を設置して、人口減少・少子高齢化社会における千葉県の活力の低下が懸念される中で、人口減少・少子化問題への対応を部局横断的に推進することとしています。
今後、統計データ等を活用し、その影響、課題、現状把握・整理等を実施し、各検討テーマごとについて協議するとともに、取組の方向性・施策の検討を行い、来年の3月には検討結果を公表するとのこと。
また、同時に並行して、各地域振興事務所単位で、管内市町村の担当者等と地域の課題を分析し、必要となる取組等についても検討し、11月頃までにはその結果を取りまとめるとのこと。
当然その結果は、3月までに発表される推進チームの結果に反映されるとのこと。
特筆されるべき点は、当該対応が「○○推進本部(本部長知事)」ではなく、「推進チーム」であり、中堅・若手職員の意見・アイデアが反映されやすいということではないでしょうか。
これまでにない、柔軟な発想の施策・取組が期待されます。
読売新聞 7月15日
人口減、15道県に対策組織…就職・婚活・育児
歯止めがかからない人口減に対し、全国の自治体に危機感が広がりつつある。
読売新聞の全国調査によると、20~39歳の若年女性の激減に伴う「自治体消滅」の可能性を指摘した5月の「日本創成会議」(座長・増田寛也元総務相)の報告後、都道府県のうち岩手県など5県が全庁的な組織を新設したほか、2県が近く設置を予定しており、同様の組織は設置済みと合わせ17道県に達した。人口減問題は多くの自治体にとって最大の課題になっており、全国知事会は15日、佐賀県で開催する全国会議で初めて、議題として取り上げる。
5月の報告後に組織を設けたのは、岩手、山形、群馬、富山、福井の5県。それ以前に設置済みは、北海道、青森、秋田、栃木、千葉、新潟、静岡、鳥取、高知、佐賀の10道県。今後、設置予定は岐阜、徳島県。
北海道は日本創成会議の報告で、2040年の若年女性の減少率ワースト10位までに6市町が入る。「人口減の要因はいくつもあり、対策を講じる上で連携の必要がある」(政策局)と4月に20課の主幹級によるワーキングチームを設置。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.07.14 - ブログ
県内の一部事務組合の6割以上が、地方自治法等で定められた、財政状況の公表を実施していないことがあみなか肇が県に依頼して実施した調査で明らかになりました。

一部事務組合とは、複数の市町村がごみ処理や水道など共同で事業を実施するもので、団体は特別地方公共団体とされており、財政状況等について条例を定め、これに基づき公表しなくてはならないこととされています。
ところが、実際に当該公表を実施している一部事務組合は約34%にとどまり、6割以上の団体が法令違反の状況にあることから、県は早急に対応を実施することとしました。
この件については、新聞各社で取上げていただくことができました。
(千葉日報 平成25年6月22日)

○6割以上の団体は法で定められた財政状況を公表せず
地方自治法第243条の3においては、「(一部事務組合の)長は、条例の定めるところにより、毎年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。」こととされています。
つまり、一部事務組合等は地方自治法上、まず財政状況の公表に関する条例を制定しなくてはならず、そして、当該条例に基づいて財政状況を公表しなくてはならない、こととされています。
ところが、今回の調査によって、財政状況を公表する義務がある32団体中、条例を制定している団体は13団体(40.6%)、当該条例に基づき公表している団体は11団体(34.4%)であることが明らかになりました。
このため、条例を制定していない団体にあってはまず条例を制定し、そのうえで財政状況を公表すること、条例は制定していても財政状況を公表していなかった団体にあってはその速やかな公表が求められます。
県内の一部事務組合等における予算・決算等の公表状況

○2割の団体は法で定められた人事行政の状況を公表せず
地方公務員法第58条の2では、「(一部事務組合の)任命権者は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。」こととされています。
つまり、一部事務組合等は地方公務員法上、まず人事行政の運営の状況の公表に関する条例を制定しなくてはならず、そして、当該条例に基づいて人事行政の状況を公表しなくてはならない、こととされています。
ところが、今回の調査によって、人事行政の状況を公表する義務がある44団体中、条例を制定し、かつ、当該条例に基づき公表している団体は35団体(79.5%)であることが明らかになりました。
このため、条例を制定していない団体にあってはまず条例を制定し、そのうえで人事行政の状況を公表することが求められます。
県内の一部事務組合等における人事行政の公表状況

○調査実施にいたる経緯
あみなか肇が一部事務組合の情報公開についてサンプル調査を実施したところ、不適切な事例が複数確認されました。
本来であれば、あみなか肇が本格的な政務調査を個人で実施するところでしたが、県の担当課もあみなか肇と同様の問題意識を共有していることを確認したことから、今回は県の担当課において、調査を実施することとなりました。
調査項目等については担当課と調整し、あみなか肇が個人で政務調査を実施したとしたときと同等とすることができました。
○一部事務組合の情報公開や機能強化に取り組みます
一部事務組合は特別地方公共団体であるものの、市町村などの普通地方公共団体と違い、住民の関心が寄せられにくい面があるものと思われます。
しかし、一部事務組合が実施している事業は、本来は個別の市町村等が実施すべき事業を複数の市町村等が合同で実施しているにすぎず、市町村等の事業そのものと言えます。
したがって、その事務の執行に当たっては、多額の公金が投入されている例も多く、市町村等と同様のチェック機能のもと、事業が執行されなくてはなりません。
これらのことから、一部事務組合は、より一層のコンプライアンス(法令順守)が求められ、そのためにも団体内部のガバナンス(統制)機能の強化が求められます。
引き続き、一部事務組合の徹底した情報公開、機能強化及び法令に則した対応が図られるよう、県に対し適切な対応を要請するとともに、あみなか肇は当該団体の対応を注視して参ります。
○積極的な情報公開と適正な税金の使われ方を厳正にチェックしていきます!
これまでも多数の政務調査を実施し、数多くの成果を出すことができたものと考えますが、引き続き、あみなか肇は可能な限りの政務調査を実施し、県民の皆様の税金の適正な使われ方やその基礎となる情報公開について監視してまいります。
そして、その結果は、随時、当ブログ及び「政務調査レポート」等を通しまして、県民の皆様に広くお伝えして参ります。
千葉県議会議員
あみなか肇
« Prev
Next »