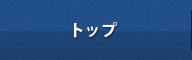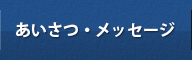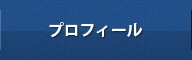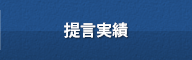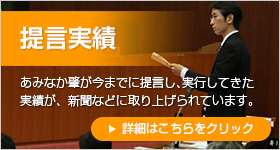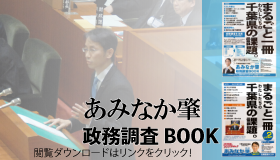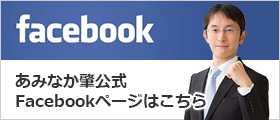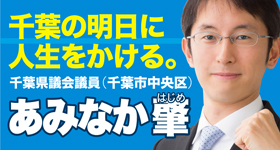2011.07.07 - ブログ
今日は、とある介護現場の責任者の方から、介護分野を中心にお話を伺うことができました。
お話いただいた中での、現在の千葉県の介護分野における主な課題は以下のとおりでした。
・福祉・介護人材の確保が重要
・定員割れしている養成校が多い
・介護職場の勤務条件等について誤解されているところがある
・社会福祉法人の介護現場ではそれほど離職率は高くない
・社会福祉法人の情報公開や経営の透明化が必要
・医療の偏在と同様に、介護にも偏在が存在する
・理学・作業療法の人材は過剰気味
・施設の定員増に対して、人材の養成数が足りない
・養成校に対してもっとお金をかけるべき
・育休等で職を離れた看護師等の介護施設等への再就職を促すような仕組みが必要
・若い人たちにとって魅力ある職場となるような工夫が必要
とのことでした。
安心して介護を受けることができる千葉県を、私たち一人ひとりの力で作り上げていかなくてはなりません。
今後、皆様とともに千葉県の介護分野の諸課題に取り組んでいきたいと考えています。
2011.07.06 - ブログ
市原市福増の福増浄水場を視察しました。

まず冒頭に、現在気がかりな、浄水場から発生する汚泥に含まれる放射性物質の値です。
福増浄水場については、当該測定値が低く、セメント等へリサイクルする業者が引き取っているとのことです。
したがって、汚泥の仮置きは実施していないとのことです。
浄水場によって汚泥に含まれる放射性物質の値に相違を生ずるのは、水源の違いによるものと思われ、高滝ダム湖を水源とする福増浄水場は当該物質が比較的少ないものと考えられます。
千葉市中央区は、利根川・印旛沼を水源とする柏井浄水場、高滝ダム湖を水源とする福増浄水場の、主に2つの浄水場から給水されています。
おおむね、千葉市役所と千葉県庁を結ぶラインの北側は柏井浄水場、南側は福増浄水場からの給水を受けているとのことです。
福増浄水場の特徴は以下のとおり。
・柏井浄水場の東側施設と同様、オゾン処理、活性炭処理の併用による高度処理を行っている
(青く光るオゾン発生装置)

・汚泥の処理は天日乾燥床で行っている
(天日乾燥床)

・自然流下によって千葉市街等へ送配水している
・高滝湖で取水してから、家庭の蛇口までおよそ1~2日程度かかる
大震災以降、蛇口をひねれば水が出て安心して飲むことができるなど、当たり前のことが当たり前にできることの大切さが、身近に感じられることが多くなりました。
2011.07.05 - ブログ
先月実施した、液状化で被災した地域の視察報告の続きです。
今回の震災では、浦安海岸の一部では、耐震護岸で地震の揺れによる被害は免れることができたものの、液状化による被害を受けてしまったとのことです。
本来は木の板のところに堤防がありましたが、写真の右側・下方に向かって移動してしまっています。つまり、液状化によって、海に向かって数メートル押し出されるとともに、数十センチ地盤沈下してしまっています。

下の写真は少し見にくいですが、護岸の先端が崩落してしまっています。

今後は埋立地における護岸及びその周辺地について、耐震策のみならず、サンドコンパクションパイル(砂杭)工法等の施工を含めた液状化対策もしっかりと実施していかなくてはなりません。
2011.07.04 - ブログ
昨日は政策研修会に参加しました。
6月20日の参議院・東日本大震災復興特別委員会における、液状化対策に係る質疑では以下のようなやりとりがあったとのこと。6月18日の総理の浦安等の液状化被害視察を受けての答弁。
小西洋之議員
(略)液状化は従来の考えでは被災者をしっかり救済できない、新しい都市型の災害である、それゆえ法律による措置、あるいは二次補正、三次補正での対応を進めるとのご発言をいただいておりますけれども、改めまして、こうした、液状化の被害救済に対する更なる総合的な対策に向けての決意を(略)
内閣総理大臣
(略)道路の補修と相まって個人の住宅についても何らかの補修ができないだろうか。そういったことを含めて、液状化に対する災害の対策の手だてを、必要な場合には制度の問題も含めて考えていかなくてはならない。(略)
今後、液状化被害等に対応した生活再建支援策の拡充、新たな災害復旧事業の創設等が強く望まれます。
時間的な制約はあるものの、早ければ7月中にも成立されるであろうとされている二次補正での早急な対応を求めたいところです。
報道等では、お盆明けから9月初め、あるいは秋にも提出されるとされている三次補正予算。遅くともここでのしっかりとした対応を期待したいものです。
2011.06.30 - ブログ
総合企画水道常任委員会の視察で柏井浄水場を訪問しました。
主要な目的は浄水場で発生する放射性物質を含んだ汚泥の仮置き状況の視察です。
写真のブルーシートで覆われたところが仮置き場です。

遮水シートや飛散防止シートが設置されるなど安全対策はなされているとのことです。
確かにしっかりと覆われていました。
数週間前から議員団の視察があると分かっているわけですから、当然といえば当然ですが・・・。
また、下の写真で柵状のものが映っていますが、これは仮囲いの設置作業中とのことです。

柏井浄水場では6月29日現在の汚泥の仮置き量は1,730トンとなっており、仮置き可能な日数はあと76日分とのことです。つまり、9月中旬には汚泥を仮置きしておく場所が場内にはなくなってしまいます。他の自治体では仮置き可能な日数がもっと短いところもあるようです。
柏井浄水場における汚泥の放射線量は6月22日現在(単位:Bq(ベクレル)/kg)、
放射性ヨウ素 放射性セシウム
Cs-134 Cs-137
東側施設 不検出 472 501
西側施設 不検出 307 334
とのこと。
国は6月16日に
8000Bq/㎏以下 → 跡地を居住地に利用しないことで埋立て可
10万Bq/㎏以下 → 住宅地と十分な距離を保ったうえで管理型処分場に仮置き可
との方針を発表しましたが、最終処分までの具体的な方法・手続きなどが明示されていません。
今後明確な基準・指針を示すよう求めていく必要があります。
また、基準等を策定したとしても、セメント等の原料として使用する会社が引き取るか、処分場側が引き取るか、地元の住民の理解が得られるかなどの問題も山積しています。
困難ですが、これらの諸課題を解決できる実効性のある対応が不可欠です。
« Prev
Next »