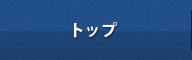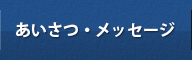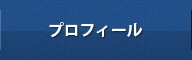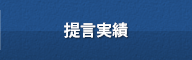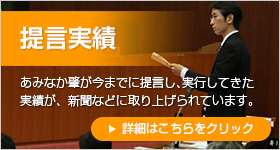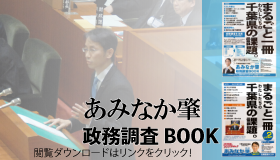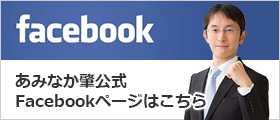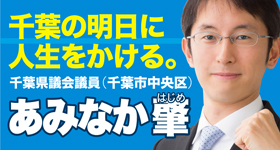2014.02.26 - ブログ
昨日から当ブログで言及している県職員の再就職状況の公表範囲及びその根拠規定。
その全国調査の概要は以下のとおりです。

まず、公表の範囲ですが、部長級以上としているのは千葉県のみ、副部長(次長)級以上としているのが岩手県のみ、そして多くの県では課長級以上としているのがわかります。
いくつかの団体は、県のあっせん制度を利用して再就職した者全員を対象とするなどしています。
残念ながら、千葉県は公表の範囲が最も狭く、ワースト1位といえるかもしれません。

次に、公表の根拠規定ですが、条例・規則、要綱・要領等を定めているのが42団体、根拠規定を有しない団体が5団体。千葉県はこの5団体の1つとなります。
これも残念ながら、千葉県を含め、5団体そろってワースト1位といえるかもしれません。
千葉県は2分野合わせて、総合でワースト1位といえるかもしれません。
こうした状況を受けて、県は、来年度中には要綱を制定し、それに基づき課長級以上を公表することとしました。
県の迅速な意思決定には敬意を表します。
引き続き、県の対応を注視してまいります。
千葉県議会議員
あみなか肇
- ブログ
昨日のブログでお知らせしました、県職員の再就職状況の公表の件。
本日の朝刊各紙で取り上げていただくことができました。
朝日新聞

毎日新聞

千葉日報

私が実施した全国調査の結果概要については、今後当ブログでお知らせいたします。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.02.25 - ブログ
本日千葉県議会において、会派の代表質問が実施されました。
その中で県は、県職員の再就職状況の公表について改善を図ることを表明しました。
具体的には、千葉県では、退職した県職員の再就職の状況については、公社等外郭団体に再就職した、部長級以上の職員に限って公表していました。
また、その公表の根拠として、要綱等を定めていませんでした。
それが本日の代表質問に対する答弁として、県職員の再就職の状況の公表については、要綱を定め、公表は課長級以上とすることとしました。

私が実施した全国調査では、公表基準を部長以上としているのは千葉県だけ、副部長(次長)以上としているのは岩手県だけ、それ以外の都道府県ではおおむね課長級以上を公表の対象としています。
また、公表の根拠も、条例、要綱、要領、指針等を定めているのが42団体で、根拠規程等を設けていないのは、千葉県を含む5道県のみとなっています。
これらのことから、再就職の公表の対象が一部の部長級以上であり、かつその根拠規程等を有しない千葉県は、この分野において全国ワースト1位といっても過言ではない状況となっていると考えられます。
しかし、今回、上記のような状況を指摘することによって、県は、早急に改善を図ることとしました。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.02.24 - ブログ
今年1月1日現在の人口が、前年同期比で1366人減少し、619万1986人となり、人口統計開始以来初めて人口が減少した平成23年から引き続いて、3年連続の人口減少となりました。

この結果、平成23年の621万7027人をピークにこの3年間で2万5041人が減少したこととなり、また、2年連続で620万人を割り込んだこととなります。
しかし、昨年中の人口減少は約1400人の減少と、平成23年、24年の1万人超の減少と比較して、その減少幅は大幅に縮小しました。ほぼ下げ止まったものと考えられます。


千葉県では、平成24年4月に「千葉県人口動態分析検討会議」を設置し、人口減少の要因について分析検討を進め、同年8月に「人口動態分析検討報告書」を取りまとめました。
それによれば、今回の人口減少は、
①東日本大震災前から現れ始めている日本全体の人口減少という長期的要因、
②都内回帰という中期的要因、
③震災の影響
という一時的要因が複合的に働いているとしています。
また、今回の人口減少は、転出の増加よりも転入の減少が大きく影響したとし、一時的要因については、緊急の対策を進めることで、液状化や放射線関連の風評を払拭し、一過性のものとして終息させる必要があるとしています。
また、人口推移に関する県の見解としては、ここ3年間の人口減少は震災を原因とする一時的なものであり、今後は県の人口推計のトレンドに戻るものとして、県内人口は今後、増加に転じ、平成29年の約626万人をピークに、その後再び減少に転ずるものとしています。
人口は、今後確実に到来する人口減少社会を維持するための社会投資を支える源であるとともに、1都3県で人口減少しているのは千葉県だけであることから、県に対し適切な対応を求めていきます。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.02.20 - ブログ
千葉県の外郭団体37団体のうち、4団体において、ハイリスクとされる「仕組債」を総額131.3億円保有しており、平成23年3月末現在で32.5億円の評価損を抱えていることが私の実施した政務調査によって初めて明らかになった問題。
この問題への対応関して、あみなか肇が示したスキームに沿って、県は適切に対応したものと一定の評価をしています。

そのスキームと県の対応は、以下のとおりです。
第1として、県は外郭団体が保有するリスク資産の現状把握をすべきということです。
これに対しては、県は外郭団体37団体に対し早急にリスク資産の保有状況について調査を実施し、リスク資産の保有状況が明らかになりました。
第2として、監査委員による監査を実施すべきということです。
これに対しても、県監査委員は外郭団体4団体に対しリスク資産の保有状況等について監査を実施し、資産運用の実態・運用体制の課題が明らかになりました。
また、大変厳しい監査結果が報告されました。
第3として、外郭団体の資産保全のため、県としての取り組みを実施すべきということです。
これに対しても、県は、平成24年10月「公社等外郭団体の適正な資金運用の確保について」と題する通知を、総務部長名で各外郭団体所管部長へ発出し、各外郭団体等の適正な資産運用体制の整備を求めるなど、県による外郭団体に対する指導・助言が実施されました。
第4として、外郭団体における資金運用規定等の整備、見直しをすべきということです。
これに対しても、各外郭団体は資金運用に関係する規程の整備・見直しを実施しました。
第5として、外郭団体の資金運用等の情報公開をすべきということです。
これに対しても、資金運用に関する情報を公開していなかった団体についても、早急に当該情報を公開しました。

これらの一連の対応で、外郭団体の資金運用に関する問題は、一定程度の改善がなされたものと考えますが、万全ではありません。
現在、調査中ですが、公社等外郭団体において、この問題にかこつけた「焼け太り」とも思える事案を認知しています。
あみなか肇は、引き続き、県及び各外郭団体の対応を注視して参ります。
千葉県議会議員
あみなか肇
« Prev
Next »