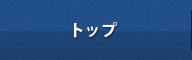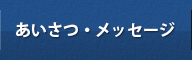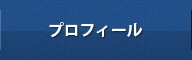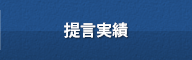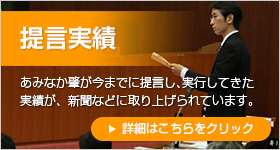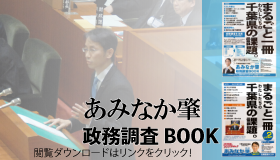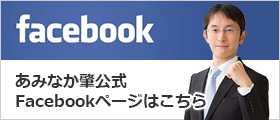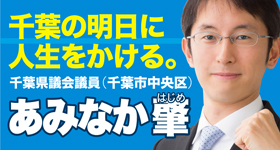2016.03.09 - HAJIMEの一歩|日々の政治活動レポート
[はじめの一歩]千葉市指定廃棄物最終処分場の県民アンケート結果報告
千葉県議会議員あみなか肇の日々の活動をレポートする「はじめの一歩」。
今回は、過日、あみなか肇政務調査レポート(指定廃棄物問題特集号)を配布し、県民の皆様に実施した指定廃棄物最終処分場問題に係るアンケートの結果報告をさせて頂きます。

「指定廃棄物最終処分場詳細調査候補地選定の撤回」を、約9割もの方が求めています!
過日、あみなか肇政務調査レポート(指定廃棄物問題特集号)を配布し、県民の皆様に指定廃棄物最終処分場問題に係るアンケートをお願いしました。
その結果、400件をも超えるご回答をお寄せいただきました。
改めまして、この場をお借りしまして御礼申し上げます。
ご回答としては、約9割の方が「指定廃棄物最終処分場詳細調査候補地選定の撤回」を求めるものでした。
この結果は千葉県及び千葉市にしっかりと伝えたいと考えます。
以下に当該アンケート結果の概要をお知らせいたします。
○指定廃棄物最終処分場に係る政務調査アンケート実施結果について(概要)
1 政務調査アンケートの実施概要
①調査目的
指定廃棄物最終処分場詳細調査候補地に千葉市中央区蘇我の東京電力千葉火力発電所敷地が選定されたことについて、千葉市中央区にお住いの方々のご意向を把握し今後の取組の参考にするため
②調査方法
アンケート用紙を新聞折込等で配布し回答を郵送で回収
③調査時期
平成27年12月15日~平成28年1月31日
④調査内容
指定廃棄物最終処分場詳細調査候補地選定に係る手法等について
⑤回答数
407件
2 調査結果のポイント
○選定の撤回を求めるべき → 357件(87.7%)
その理由(重複有)
・選定手法がおかしい → 284件 (69.8%)
・津波のリスク → 261件 (64.1%)
・液状化のリスク → 265件 (65.1%)
・東京湾に隣接するリスク → 241件 (59.2%)
・工場地帯に隣接するリスク → 223件 (54.8%)
・人口密集地に隣接するリスク → 317件 (77.9%)
・千葉市の分は千葉市で処分すべき → 136件 (38.1%)
(「撤回」に占める割合)
○千葉市で受け入れるべき → 33件 ( 8.1%)
○その他 → 17件 ( 4.3%)
3 今後の対応
今回の政務調査アンケートの結果を踏まえまして、千葉県、及び千葉市に対して、環境省に対し指定廃棄物最終処分場詳細調査候補地の選定を撤回するよう求めるとともに、あらためて保管自治体での分散保管を検討するなど、住民の意見に十分配慮した対応を求めていくよう協議することを、強く要望して参ります。

※皆さまからお寄せ頂いた400件以上の実際のアンケート。ご協力本当にありがとうございました。
以上、HAJIMEの一歩でした。
千葉の明日に人生をかける
千葉県議会議員(千葉市中央区)
あみなか肇
- あみなか'sEYE|あみなか視点の政治コラム
[あみなか’S EYE!]自治体独自の被災者生活再建支援制度について
千葉県議会議員あみなか肇が独自の視点で千葉県の政治や暮らしについて綴る「あみなか’S EYE!」。 第二回目は「自治体独自の被災者生活再建支援制度」についてお話しいたします。

※画像はイメージです。
千葉県の被災者生活再建支援制度の適用要件の緩和を、強く県に要望します
ここ数年、千葉市では東日本大震災を除き、住家の全壊被害が生じるような大きな災害は発生していませんでしたが、平成27年9月6日に蘇我地区を中心に発生した強風災害では、その範囲は狭かったものの、住家の全壊など大きな被害が生じました。
しかし、今回の災害で生じた被害では、被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)が定める要件に達せず、同法が適用されませんでした。
このため、当該被災世帯に対する支援としては、市の災害見舞金の支給にとどまることとなりました。
そこで、千葉市は全壊世帯が生じた大きな被害であったことを鑑み、被災世帯に対し独自の支援金を支給することとし、その生活再建を支援することとしました。
なお、支援法の概要は以下のとおりとなっています。
○国の生活再建支援制度の概要
(1)適用要件
一市町村で10世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合など
(2)対象世帯
全壊した世帯、大規模半壊した世帯、半壊以下で解体した世帯
(3)支援金額
基礎支援金として全壊100万円、大規模半壊50万円、半壊等解体100万円となっており、加算支援金として建築・購入200万円、補修100万円、賃借50万円が住宅の再建方法に応じて支給される。
また、千葉県は国の同制度の適用要件を一部緩和した、独自の被災者生活再建支援制度を有しており、具体的には、一市町村で10世帯以上の全壊被害が発生していなくても、連たんする複数の市町村で合計10世帯以上の全壊被害が発生した場合などには適用されることとなっています。
しかし、今回の千葉市の強風による被害は、住家全壊2世帯であり、国及び千葉県の被災者生活再建支援制度は適用されません。
このため、上記のとおり、千葉市が単独で生活再建支援制度を策定、適用し、被災世帯の生活再建を支援することとなりました。
このことについて県の担当者にヒアリングしたところ、県としては県の支援制度の要件を満たさないことから関知しない、また要件緩和は一切考えていないとのことでした。
ここで、他都道府県の独自の生活再建支援制度の策定状況を政務調査しました。詳細は以下のとおりです。
(図1)

概要を見ると、6種類程度に分類されるものと考えます(府県数は重複有)。
①住家全壊等が1世帯以上から適用
→8県(ただし、宮崎県は「見舞金」に近い。)
②複数世帯の住家被害から適用
→2県
③支援法等が適用されることとなった災害であって、その適用外となった市町村に適用
→7府県
④一般的な制度として策定するも、その適用の可否についてはその都度判断
→1県
⑤共済制度として策定
→1県
⑥特定の災害に着目して策定(事後的)
→9府県
これらを見ると、都道府県によって大きな差異があることが分かります。
全壊被害1世帯から適用し、300万円を支援金として支給する自治体があれば、当該制度を全く有しない自治体もあります。
また、千葉県の隣接県で見ると、埼玉県及び茨城県の当該制度の充実が顕著です。
例えば、何らかの災害によって、千葉県、埼玉県及び茨城県の県境付近でそれぞれ3世帯ずつ、計9世帯の全壊被害が発生したとすると、埼玉県及び茨城県の被災6世帯は各県の支援金(各世帯300万円)を受取ることができますが、千葉県の被災3世帯は千葉県からは一切の支援はありません。
現在、私は、千葉県の被災者生活再建支援制度の適用要件の緩和について強く県に要望しています。
このように自治体の施策には大きな相違があることがよくあります。
こうした相違を県民の皆様に発信し、どのように変えるべきなのか、あるいは変えないのか、しっかりとご意見を拝聴し、県政に反映させていきたいと思っております。
以上、あみなか’S EYE!でした。
千葉の明日に人生をかける
千葉県議会議員(千葉市中央区)
あみなか肇
2016.03.02 - THE TAIDAN|これからの千葉を語る対談シリーズ
THE TAIDAN
[VOL2]若者の本音を探る!次世代を担う若者たちの声
あみなか肇 × 千葉県の大学生Part.2 |

次世代を担う今の若者たち。
彼らにとって、今の日本はどう映り、そして将来をどう考えているのでしょうか?
今、生活する上での悩みや不安、就職や結婚など将来のこと。
今回はPart.2として、千葉県や千葉市のイメージや魅力に対する若者たちの声をお届けします!
対談日:2016年12月14日
(さらに…)
2016.01.20 - あみなか'sEYE|あみなか視点の政治コラム
[あみなか’S EYE!]大学生の”学び”と”お金”の悩み
千葉県議会議員あみなか肇が独自の視点で千葉県の政治や暮らしについて綴る「あみなか’S EYE!」。 第一回目は「奨学金」についてお話しいたします。

過日、学生の皆さんとの議論の中で、
“将来が不安だからこそ今しっかり勉強をする!”
というお話がありました。
そして、勉強するにはお金がかかる、留学するにもお金がかかる、
ということも耳にしました。
“将来への不安”に備え、留学などを含めて、しっかりと勉強したいが、経済的な面で懸念があるということ、と受け止めました。
いつの時代も、学びとそれに先立つ「お金」は学生にとって大きな悩みの一つです。
そこで、現在の大学生の皆さんを取り巻く学習環境を、奨学金を中心に経済的な面から検討します。
家計と大学授業料の状況について
まず、図表1は近年の家計(民間平均賃金額 ※年間ベース)を見たものです。
※以下、簡略化のため物価の上昇は考慮せず名目での比較とします。
(図表1)

※国税庁民間給与実態統計調査結果から作成
平成10年を頂点に、平均賃金は平成10年まで逓増し、その後約10年間は減少し続けましたが、ここ数年は上昇に転じています。
次に図表2は大学授業料の推移です。
平成元年からの16年間で、国立で18万円、私立で約25万円の増加となっています。
(図表2)

※文部科学省資料国立大学と私立大学の授業料等の推移から作成
統計の時期は異なりますが、民間平均賃金額が下落する中で、大学授業料は上昇しているという状況を読み取ることができます。
奨学金の受給状況について
図表3は大学昼間部における奨学金受給率の推移です。
平成6年には2割程度だったものが、平成24年には5割を超える受給率となっています。
(図表3)

※(独)日本学生支援機構学生生活調査報告から作成
図表4は奨学金受給者に占める、給付・貸与別の比率を示しています。
9割以上が貸与型を受給しています。
(図表4)

※文部科学省(独)日本学生支援機構奨学金貸与事業の概要から作成
図表5は奨学金の受給者数、有利子・無利子別の内訳を示したものです。
平成15年度を境に有利子奨学金が無利子奨学金を上回り、平成24年度には奨学金利用者の3分の2は有利子の奨学金を利用するものとなっています。
(図表5)

※文部科学省(独)日本学生支援機構奨学金貸与事業の概要から作成
大学授業料と奨学金の状況
図表6は各国の大学授業料と奨学金等の公的支援の状況を示したものです。
縦軸は授業料の高い・低いを、横軸は奨学金等の公的支援の高い・低いを示しています。
4つのゾーンに分けてその特徴を見ると以下のとおりとなります。
(図表6)

※OECD Indicators Education At a Glance 2014から一部加工。
| 1ゾーン |
授業料が0か安い |
奨学金等が充実 |
| 2ゾーン |
授業料が0か安い |
奨学金等が充実していない |
| 3ゾーン |
授業料が高い |
奨学金等が充実 |
| 4ゾーン |
授業料が高い |
奨学金等が充実していない |
日本は、4ゾーンに属し、授業料が高く、奨学金等が充実していないという区分に分類されるようです。
以上、大学生を取り巻く経済的な面について、奨学金を主としてその概略を検討しましたが、対談の中でも出てきたご指摘が、各種統計などによっても裏付けされています。
高等教育のあり方、奨学金制度のあり方などについて、限りある財源の中でこうした分野に対する支出をどうするのか、今後より積極的に議論を深めて行く必要があると考えます。
以上、あみなか’S EYE!でした。
>関連記事:[THE TAIDAN]若者の本音を探る!次世代を担う若者たちの声
千葉の明日に人生をかける
千葉県議会議員(千葉市中央区)
あみなか肇
- HAJIMEの一歩|日々の政治活動レポート
[はじめの一歩]議員の勉強会について
千葉県議会議員あみなか肇の日々の活動をレポートする「はじめの一歩」。
今回は、議員の勉強会についてお話しいたします。

議会毎に知事(県)から提案される議案について、その概要は議案書に記載されています。しかし、議案書にはページ数等の制約があることから、議案の内容について詳細には記載されていません。
このため、議案の内容についてより詳細に知るためには「勉強会」を実施することとなります。「勉強会」の開催にあたっては、当該議案を提案した担当課の職員から詳細な説明を受けることとます。
また、議案以外でも、報道等で取上げられ県民の皆様の関心が高いと思われるもの、議案としては提案されてはいないものの県として対応すべきと考えられるもの等について、「勉強会」を実施し県としての考え方を質すことがあります。
各議員がどの程度「勉強会」を実施するかは、各議員の個性もあり、議員によって大きな差があるようです。私の場合は、ほぼ毎週、多いときには毎日のように実施することもあります。
私が「勉強会」で県の担当者に確認するポイントは主として以下のような点になります。
・県民の意見は聞いたのか
・他の都道府県ではどうしているのか
・県がすべき事業なのか。国、県、市町村のどのレベルで実施すべきか。民間活用は検討したか
・同様の事業を市町村が実施している場合、市町村ではどのようにしているのか
・財源はどうなっているのか
・民間企業だったらどうしているのか
・法的な整合性はとれているのか
・経済学的な観点からみて、社会的厚生を損ねていることはないか
・社会的な公平・公正の観点からはどうか
・事業の予算額だけではなく間接費用等を含めた総費用と事業の便益は見合っているか
・自治体として社会的責任を果たしているのか 等々。
一つの論点でも、複数の部・課にまたがることが多々あり、対応に苦慮することもかなり多くあります。たとえば、再生可能エネルギーについて、全般的には商工労働部、バイオマス発電のうち廃棄物系については環境生活部、間伐材系については農林水産部が担当となります。3部にまたがり、さらにその部の下で事業によって課で分かれることとなります。
県行政をより良くするためには、県の事業を良く知り、上記のポイント等の観点から改善を促すことが必要となります。そのための第一歩が「勉強会」ということになります。
以上、HAJIMEの一歩でした。
千葉の明日に人生をかける
千葉県議会議員(千葉市中央区)
あみなか肇
Next »