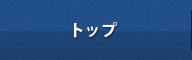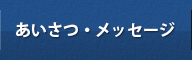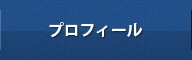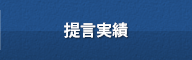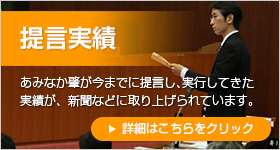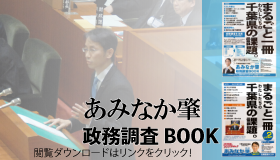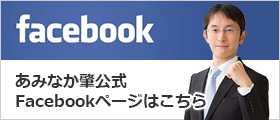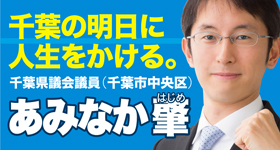2014.03.21 - ブログ
千葉県では、千葉県水道局が京葉・東葛地域の11市(千葉市・船橋市・市川市・習志野市・松戸市・市原市・鎌ヶ谷市・浦安市・成田市・印西市・白井市)、県内人口の半分近い約300万人に末端給水事業を実施しており、全国的にみても3番目に大規模な水道事業体となっています。(図表1 図表2)
図表1

図表2 千葉県水道局 給水市町村別内訳

(千葉県水道局ホームページより 平成23年3月現在)
その一方で、下水道事業は上記11市が個別に経営しています。
このため、上水道料金は千葉県水道局が、下水道使用料金は各市がそれぞれ別々に請求・徴収することとなっています。
全国的にみると政令指定都市(千葉市を除く)及び人口20万人以上の都市(千葉県水道局給水区域を除く)では、上・下水道料金の徴収一元化が行なわれているとのことです。
したがって、千葉県水道局給水エリアのように、比較的大規模な都市部において、上水道と下水道使用料金が別々に請求・徴収されているのは、稀なケースといえます。
上・下水道料金の徴収一元化のメリットは熊谷俊人千葉市長が力説しておりますが、以下の3点に集約できるものと考えます。
●住民サービス向上効果
これは各種手続きにおいて、それぞれ県水道局及び市下水道担当部局への2重の手間を重ねることがなくなり、利便性が向上する効果です。
●徴収率向上効果
水道料金の未納に対しては、水道を止めることによって、支払いを強く促すことができるものの、下水道は使用を差し止めることができないことから、水道と比較して、その徴収率が低くなってしまう傾向があります。
そこで、上・下水道料金の徴収を一元化することによって、下水道料金の徴収率を高めることが期待できる効果です。
●コスト削減効果
印刷物・郵送代の削減や、11市で別々に稼動している料金徴収システムの維持費の削減など、徴収に要する事務コストを削減することができる効果です。
≪その2に続く≫
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.03.17 - ブログ
千葉県は平成26年度予算において、県内の医師不足の解消を促進するため、医師修学資金貸付制度について、新たな貸付制度を創設しました。

これまでの医師修学資金貸付事業は、千葉大学、順天堂大学、日本医科大学、帝京大学の医学部生で、将来、千葉県内の医療機関に従事しようとする者を対象としていました。
しかし、今後急速な高齢化の進展に伴う医療需要の増大が見込まれることから、県は、他県の医学部に入学した千葉県出身者のUターンを促し、県内病院での就業に結びつけるため、これまでの貸付制度に加えて、新たに「ふるさと医師支援コース」を設置しました。予算額は1800万円となっています。
○新設「ふるさと医師支援コース」の概要
・貸付対象 県外大学医学部に入学した学生(千葉県出身者)で、将来、県内医療機関に就業しようとするもの。
・貸付人数 10人
・貸付額 15万円(月額) (180万円(年額))
・貸付期間 6年間(医学部の修学年数)
・返還免除 知事が指定する医療機関(県内)で、9年間従事した場合

県の試算では、これら医師修学資金貸付制度によって、平成37年度までに315人の医師を確保することができると見込んでいます。(内訳:既存制度255人 ふるさと医師支援コース60人)
本県の医師不足の現状としては、すでにご案内のとおり、全国でも人口当たりの医師数が全国ワースト3位となっています。実効的な医師確保策を求めていく必要があります。

また、県においては、月内にも、千葉大学医学部付属病院に委託した「千葉県医師・看護職員長期需要調査」の結果を発表することとなっています。
当該調査では医療圏別、施設の種類別、診療科別等の区分での需要側の推計等が実施されるものとしています。
このように、今後必要とされる医師・看護職員の長期の需要数を算出し、それに基づき、今後の具体的な確保策を検討することは大変重要であると考えます。
県からの調査結果の報告があり次第、当ブログでも取り上げたいと考えています。
千葉県議会議員
あみなか肇
- ブログ
先日ご紹介した、上下水道料金の徴収一元化について、千
葉日報で取り上げられています。

(千葉日報 3月14日)
http://www.chibanippo.co.jp/news/politics/183857
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.03.13 - ブログ
3月13日、県議会総合企画水道常任委員会が開催されました。

同委員会で千葉県水道局は上下水道料金の徴収一元化について言及し、月内にも開催予定の関係市町村で構成される「下水道使用料等事務連絡協議会」での議論を経て、平成29年度中の徴収一元化の実施を目指し対応していくとのことでした。
個人的には、あみなか肇が想定していた実施時期よりも早いものであり、県水道局の対応を評価したいと思います。
引き続き、徴収一元化の確実な実施に向けて、県水道局の対応を注視してまいります。
千葉県議会議員
あみなか肇
- ブログ
県が事務局業務を担うなど、県が主体的に関与する任意団体(例として「千葉県○○協議会」、「千葉県○○協会」等)の運営状況、特に会計面について、あみなか肇は独自の政務調査を実施し、その結果を県議会で一般質問し、運営の適正化を促したところ、新聞で取り上げていただくことができました。

(平成24年3月1日 朝日新聞 千葉版)
政務調査を実施した理由は、こうした団体にあっては、税金を原資とする県費が投入されており、会計処理が適正になされているかどうかを確認しなくてはならないと考えたからです。
また、それらの団体の数、従事している県職員の人数、投入されている県費の額などについて、県は実態を把握していないということも大きな理由の一つです。
調査結果は、団体数45団体、歳入総額は約37億1000万円、補助金・負担金・交付金・委託料・その他会費などとしての県費の投入額約25億6000万円、歳入総額に占める県費投入額の割合約70%、県職員の従事状況は、役員として73人、職員として226人でした。
また、以下のような適切さを欠くと考えられる事例がありました。
事例1 決裁権限及び会計に係る規程が無いもの。あるいはあっても慣例で県準拠とされており明文の規程が無いもの
事例2 団体の印鑑の管理を管理職員ではなく、一般職員が行っているもの
事例3 団体の通帳の保管責任者と、印鑑の管理者が同一人であるもの
事例4 監事・監査が複数人でないもの
これらの団体は、県の庁舎内に事務局を置き、県職員が役員や職員として従事している以上、我々県民の目には県と一体のものとして映っていること、団体の多くが県民が負担する税を原資とする財政的支援を受けていることから、より一層の透明性の確保、情報公開、説明責任が求められるものと考えます。
あみなか肇は税金の使われ方について、引き続き厳しく監視するとともに、政務調査を積極的に活用する県議会議員として活動して参ります。
千葉県議会議員
あみなか肇
« Prev
Next »