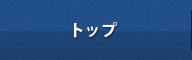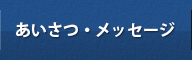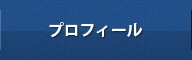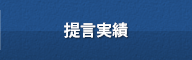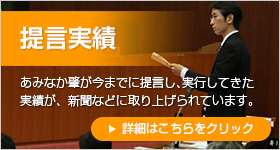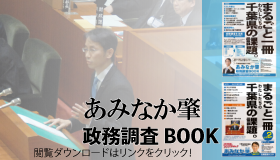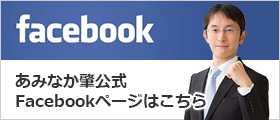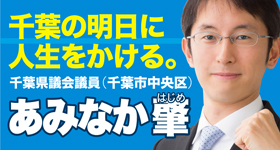2014.11.20 - ブログ
ちょうど一週間前に当ブログで言及した解散総選挙による県議会の日程変更について、懸念していたとおりの展開となってしまいました。
事前のマスコミ報道どおり、18日夜、総理は、衆議院を21日に解散し、総選挙を12月2日公示、14日投開票の日程で行う旨表明しました。
そして、先日、千葉県議会議会運営員会が開催され、県議会日程が変更されることとなりました。
具体的には、12月2日(選挙公示日)の代表質問初日以降を順次繰り下げる。
常任委員会を4つずつ、2日(12月15日、16日)で終わらせるなどです。
大変残念ながら、国政の影響を受け、県議会の日程を変更し、県民の皆様にご迷惑をおかけすることとなってしまいました。
力不足でありますが、今後はこうしたことが無いよう取組んで参ります。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.11.17 - ブログ
全国初となるヤード条例が12月県議会(11月26日開会)に提案されることとなりました。

当初、9月議会に提案される段取りでしたが、罰則部分について検察庁との協議が整わず、3か月ずれ込んでの提案となりました。
千葉県の自動車盗の認知件数は、近年全国ワーストレベルで推移しており、特に平成25年の認知件数は3,295件と全国ワースト1位となっています。

その原因の一つが、県内に全国で最も多く存在するヤード(鉄板や塀などで囲われた自動車の解体工場)の存在が指摘されています。

ほとんどのヤードは健全に事業を行っていますが、ごく一部のヤードにおいて自動車窃盗グループがヤード経営者と結託をして、盗難車の解体作業場に利用している実態があります。
また、ヤードにおいて廃油や廃液等で周辺環境を汚染している例も見られ、平成17~25年度で62件が発生しているとのことです。
これらのことから、県では、県民の生活環境の保全上の支障の防止、県民の平穏な生活の確保を図るため、ヤード条例を12月議会に提案しました。
あみなか肇は、2年9か月前の平成24年2月議会一般質問において、総合的なヤード対策・自動車盗対策に取り組むことを強く要望し、その後も粘り強く訴えて来ましたが、このたび、ようやくヤード条例の制定という形で実現しました。
引き続き、県及び県警のより積極的な対応を要望して参ります。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.11.13 - ブログ
今日現在、マスコミ等では年内のいわゆる解散総選挙について多く報道されています。
仮に報道通りの総選挙が実施されることとなった場合、以下のような点が懸念されます。
今から約2年前、平成24年11月16日に衆議院が解散され、同年12月4日公示、16日に衆議院議員総選挙が施行されました。

当該選挙期間中は12月定例千葉県議会の日程とも重なっていたため、県議会は当初予定されていた日程を変更した経緯があります。
具体的には、
①総選挙の公示日と同日に予定されていた県議会の一般質問日を休会日にし、質問日を翌日以降に繰り延べた
②通常2委員会ずつ4日間開催する常任委員会を、8委員会まとめて1日で実施した
等です。
常任委員会を複数の日にわたって開催するのは、県民の皆様が各委員会の傍聴を可能とするためというのも理由の一つであるはずです。
千葉県には千葉県の課題が存在し、これを熟議する県議会が、国政の影響を受け、その日程等を変更し、県民の皆様にご迷惑をおかけすることは大変残念なことです。
「地方自治の自殺」とも指摘されかねません。
仮に、年内の総選挙が実施されることとなった場合、個人的には、こうした対応が今回の総選挙でなされることがないようにしていきたいと考えています。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.11.10 - ブログ
千葉県庁の女性管理職の割合は平成25年4月1日現在で3.9%、県内市町村の女性管理職の割合は平均で9.0%であることが、あみなか肇の県議会一般質問で明らかになりました(内閣府調査による)。

県庁における女性登用について、市町村よりも進んでいない実態が判明しました。
なお、平成25年4月現在、県内54市町村のうち、女性管理職が1人もいないのは12市町であることも明らかになりました(下表参照)。

また、県庁の知事部局に勤務する50歳以上の職員について、男女別に、人数、管理職員の人数、管理職の割合を示したものが下の表です(あみなか肇が県に依頼して実施した調査による)。

それによれば、男性職員は6割近くが管理職であるのに対して、女性職員の管理職の割合は2割に満たない状況となっています。
管理職への登用については、男女を問わず、能力、実績等を総合的に考慮しながら、適材適所を基本に任用すべきと考えます。
しかし、県の業務は県民に身近な、子育て、教育、介護等も多く、女性目線を活かした企画立案業務等も多く存在するものと考えます。
女性職員の活用について、県に対し、多様な職務経験、研修による能力開発、仕事と家庭の両立支援等に取り組み、管理職への積極的な登用に努め、もって県民が暮らしやすい施策を実施することができるような人事制度を要望して参ります。
千葉県議会議員
あみなか肇
2014.11.06 - ブログ
通常、地方公務員の異動については、人事担当課が、職員の意向を調査し、それを踏まえたうえで、内示し、異動するという流れが一般的となっています。

しかし、こうした通常の異動の他に、庁内人事の活性化等の観点から、各種の人事施策が実施されています。
県では、その一つとして庁内公募制度を採用しています。
庁内公募には2種類あります。
1つとして、県が政策課題等など業務を提示して、希望する職員を公募する人材募集型。
2つとして、職員自らが希望のする業務を選択して応募する業務選択型。
それぞれについて、平成25年度における対象者、応募者、実際の配属者の状況をまとめると以下のとおりとなります。

人材募集型では、対象者7000人のうち、実際に配属された職員は1人、業務選択型では、対象者6000人のうち、実際に配属された職員は5人、合計しても6人というのは、私見ではとても少ないと感じます。
県の「人財開発基本方針」では目指すべき職員像として、創造性とチャレンジ精神を持ち政策を立案・遂行する職員が掲げられています。また、同時に、風通しの良い、職場風土づくりにも言及しています。
庁内公募が低調な原因の一つとして、「出る杭は打たれる」「だから目立たないように」とか、「積極的にこれをやりたいと手を挙げて、失敗したら出世に響く」とか、「与えられた仕事をただこなしていればいい」とか、「事なかれ主義」といった職場の風潮があるのではないかと感ぜられます。
積極性を持った、ヤル気のある所属、職員が報われるような庁内公募制度の活用、利用者の大幅な増加、その前提となる風通しのいい職場づくりなど、公務能率向上のための職場環境の改善を強く要望して参ります。
千葉県議会議員
あみなか肇
« Prev
Next »