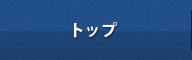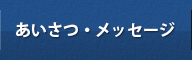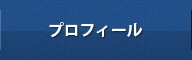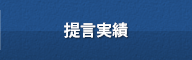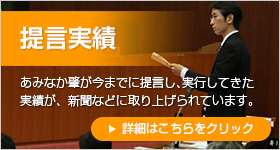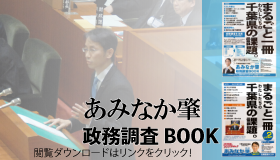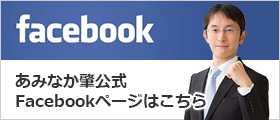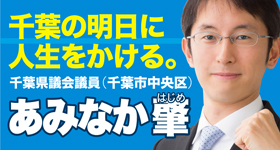子ども医療費助成制度の拡充を!
2014.02.10 - ブログ
私と同世代の子育て中の親御様から、「他県の子ども医療費助成は充実しているのに、千葉県は・・・」、「子ども医療費助成が充実すれば、より安心して子育てできる・・・」などといったご意見を頂戴することが多くあります。
子ども医療費助成制度は、乳幼児や小・中学生等の医療費の患者負担分を自治体が助成する制度で、患者世帯の経済的負担を軽減する、又はゼロにするという制度です。つまり自治体による「子どもの医療費無料化」といえる制度です。
現行の公的医療保険制度では、子どもが医療機関の窓口で支払う自己負担率は2割若しくは3割となっていますが、子ども医療費助成制度は、患者の自己負担部分を自治体の公費でカバーするものです。
この制度は、すべての都道府県で実施されている(助成対象年齢等にはかなりの差がある。)ものの、国からの財政的な援助は全くなく、すべて都道府県及び市町村の独自事業として実施されています。このため、自治体によって制度の内容が異なります。
また、制度の実施主体は市町村ですが、その費用は都道府県も負担しています。
なお、千葉県では、子ども医療費助成制度に要する経費について、県が制度化している部分については、県と市町村が2分の1ずつ負担しています(千葉市を除く。政令指定都市である千葉市の子ども医療費助成に係る経費のうち、県が負担するのは4分の1)。
そして、市町村が独自に実施している、県の制度を超える部分については、市町村がすべて負担することとなります。
そこで、まず、千葉県の子ども医療費助成制度をみると、入院については中学校3年生まで、通院については小学校3年生までが助成対象となっています。
これらの助成対象を、全国と比較したものが以下の表です。
都道府県の子ども医療費助成制度の実施状況
平成25年12月現在
千葉県は、入院については、全国トップ(福島県は原発事故の特殊要因があるため、ここでは考慮しない。)となっています。
同様に通院をみると、最も充実している都道府県は中学校3年生、その次が小学校6年生、その次が小学校3年生であり、千葉県は3番手に属していることが分かります。
したがって、千葉県の子ども医療費助成を全国レベルでみると、入院については全国でも最も充実しており、通院についてもそれなりに充実しているものの、まだ拡充の余地がある、といった位置づけであると考えます。
次に、県内の市町村の状況をみたものが、以下の表です。
千葉県内の市町村の子ども医療費助成の実施状況
平成25年12月現在
いすみ市が入院・通院ともに高校3年生まで、一宮町が入院・通院ともに高校1年生までと、これら2市町の助成対象が突出していることがわかります。
また、入院については、上記2市町以外の52市町村は中学3年までに集中している一方、通院については、小学3年、小学6年、中学3年の3つに分散しており、最も多いのが中学3年の32市町村となっています。
これらを見ると、財政的に豊かな自治体が、助成対象の範囲を広げているともいえず、様々な要因、例えば、近隣市の状況等によって大きな影響を受けているものと考えられます。
今後のこの制度の拡充の方向性、及び県と市町村の費用負担のあり方ですが、都道府県レベルで見れば、すべての都道府県で当該助成事業を実施しており、その助成範囲としては小学校就学前が最も多くなっています。
これら県民のニーズを踏まえて全国的に広く実施され定着しているものについては、もはや国民的ニーズがあるといえることから、この部分までは国の事業として実施し、国が費用負担するということも考えられるのではないでしょうか。
そして、千葉県内の市町村の場合、入院、通院ともに、助成対象として最も多いのは中学3年であることから、国が負担すべきと考える小学校就学前を超える部分から中学3年までは、県と市町村で2分の1ずつの費用負担とし、それを上回る部分は市町村の独自事業として市町村が負担するということも考えられます。
そうすることによって、国・県・市町村の役割・財源負担を整理するとともに、千葉県の子ども医療費助成の対象を、自治体の負担を増加させることなく、入院・通院ともに中学3年生までに拡充することができるのではないでしょうか。
千葉県議会議員
あみなか肇