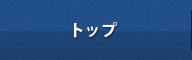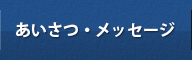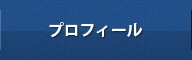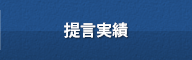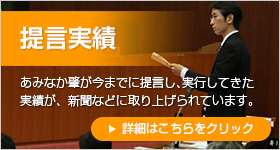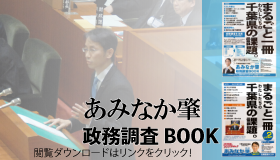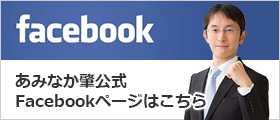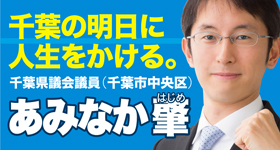県による踏切事故の防止対策を!
2014.07.31 - ブログ
7月11日に流鉄流山線の踏切(松戸市大谷口)で電車と乗用車の衝突事故が発生し、乗用車に乗っていた夫婦お二人が亡くなられました。
この踏切は遮断機や警報機が設置されていない、第4種踏切であったとのこと。
また、先日、市原市八幡海岸通の京葉臨海鉄道貨物線白旗踏切において、貨物列車とトラックが衝突したものの、幸いけが人はいませんでした。
報道によれば、この踏切は遮断機が設置されていないとのこと。
このように、最近、県内における遮断機のない踏切(第3種)、或いは遮断機及び警報機のない踏切(第4種)における事故が発生しています。
これらを踏まえ、県内における踏切の状況を県に確認したところ、データは持ち合わせておらず、また、以前、国土交通省が実施した踏切に係る調査も廃棄済みでやはりデータは無いとのことでした。
他県では、県が主催で踏切事故対策会議が開催され、鉄道事業者、沿線自治体が参加し、踏切の改良等について協議された例もあるようです。
警報機も遮断機もある踏切(第1種)に比べれば、第3・4種踏切は数は多くないものの、事故の発生率は高いとの指摘もあります。
踏切の問題については、一義的には鉄道事業者と道路管理者の問題であり、県の関わりとしては道路管理者たる県道以外の踏切は無関係とも言えますが、県内全体を俯瞰しつつ、踏切の安全確保を図ることは重要であると考えます。
県内の踏切(特に第3種・第4種)における事故が連続して発生したという事実がある中で、あみなか肇は、県による県内の踏切の安全対策を実施すべきであると考えますが、県民の皆様はどのようにお考えになるでしょうか。
千葉県議会議員
あみなか肇